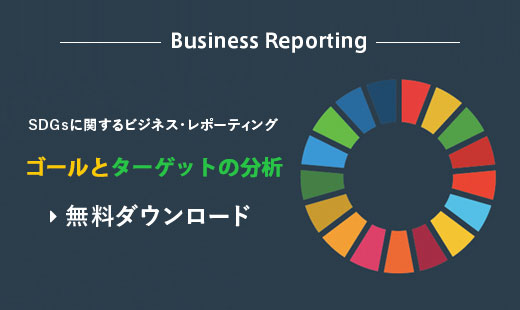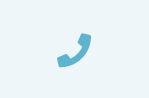目次
1.SDGsは国際的な開発目標
2.SDGsの「持続可能な開発」の意味は
3.SDGsの策定経緯
4.SDGsの推進体制
5.SDGsに企業が取り組む理由
6.SDGsがもたらす途上国でのビジネスチャンス
7.SDGsとCSV事業
8.SDGs官民連携プログラムの活用
SDGsは国際的な開発目標
SDGs(持続可能な開発目標)とは、2015年の国連サミットで「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた、国際的な開発目標のことです。世界の150か国を超える加盟国首脳の参加のもと、全会一致で採択されました。

貧困、飢餓、ジェンダー、教育、環境、経済成長、人権など、幅広いテーマをカバーしており、2030年までの達成が目指されています。豊かさを追求しながら、地球環境問題に対処し、「誰一人取り残さないこと」が強調されています。
SDGsの登場の背景には、近年の地球環境や経済・社会の持続可能性に関する世界的な危機意識の高まりがあります。国連で合意された国際的な開発目標には、これまでもいくつものアジェンダがありました。SDGsの前身であるMDGsがその代表的なものです。従来は、こうした開発アジェンダは、国や国際機関やNGOなどが対処するものという考え方が一般的でした。
しかし、近年は地球環境問題や経済・社会問題は、より深刻で影響が拡大し、政府や国際機関だけでは対処できなくなりつつあります。企業、市民社会、メディア、教育機関などの様々な組織の積極的な関与が必要となっています。特に、企業は環境、社会、経済への影響力が大きく、業務体制の変革やイノベーションを通じて様々な課題に取り組むことができます。
また、こうした取り組みを通じて、企業自身も未来を見据えた持続可能な経営を志向することも可能となります。SDGsは、企業に対し、ビジネスを通じて環境、社会、経済の諸課題に取り組むことを期待しています。
SDGsの「持続可能な開発」の意味は
SDGsという言葉は、徐々に日本社会に浸透しつつあるように見えますが、そもそも「持続可能な開発」とは何を意味するのでしょうか。持続可能な開発があるのですから、持続可能で無い開発があるはずですが、それはいったい何を意味するのでしょうか。持続可能な開発の意味について考えてみます。

まず「開発」とはどう定義されるのでしょうか。「開発」はDevelopmentの和訳ですが、これは「発展」とも訳されます。所得水準が低い国(Developing Countries)のことを、開発途上国といったり発展途上国といったりします。両者の間で若干のニュアンスの違いはあるのかもしれませんが、開発と発展は同じように使われています。
開発という概念は、経済開発、社会開発、地域開発、農村開発、人的資源開発など、様々なケースで使われます。経済や社会、地域、農村、人的資源のそれぞれが「開発」されることにより、何らかの価値が高まって、以前よりも良い状況に至るという意味が込められています。
一方、同じような概念で成長(Growth)があります。これは開発とは異なり、経済規模の拡大とか、所得水準の上昇など、数値の上昇を示す用途で使われます。経済成長という言葉はありますが、社会成長とか地域成長、農村成長という言葉は耳にしません。
それでは、「持続可能な開発」とはどう定義されるのでしょうか。これを考えるヒントはSDGs合意の背景文書の一つであるリオ宣言(「環境と開発に関するリオ宣言」、国連環境開発会議、1992年)に見いだされます。この宣言には全部で27の原則がありますが、その第一原則の中で、「人類は、持続可能な開発への関心の中心」にあると記されています。そして、持続可能な開発とは「自然と調和しつつ健康で生産的な生活を送る」ことであると示されます。
持続可能な開発とは、無作為のままでは達成されることはなく、人類はいくつかの重要課題に協力して取り組む必要があります。具体的には、「環境保護(第四原則)」、「貧困の撲滅(第五原則)」、「生態系の保全、保護、修復(第七原則)」です。現在の「生産及び消費の様式」の中には持続可能でないものがあり、それを減らしてゆかねばなりません。
従来のままの「生産」、「消費」を繰り返していたら、その影響は、地球規模の環境の悪化や、貧困の深刻化、生態系の破壊などの形で現れることになります。これでは、人類は持続可能な開発を進めることが難しくなります。「持続可能な開発」には、こういうメッセ―ジが込められています。
また、「持続可能な開発」の定義を考えるうえで、もう一つのポイントは時間軸です。これまでの「開発」は、せいぜい数年から10年くらいまでの中期的な時間軸で考えられていました。国や自治体の開発計画は五か年計画が一般的です。世界銀行のような国際協力機関の国別支援戦略もだいたい五か年が区切となっています。「開発」を進めることにより、今現在の人々の生活を改善すること、今日の社会や環境面のトラブルを解決することが基本的には目指されています。
しかし、「持続可能な開発」では、もう少し長い時間軸で環境や社会の課題がとらえられているように考えられます。たとえば、2015年パリのCOP21において採択された「パリ協定」では、2030年以降の温室効果ガス排出削減までもが協議の対象とされます。さらに、今世紀末時点での世界の平均気温の上昇幅を抑えることが最終的な目標になっています。現在の世代の人々ではなく、子供や孫といった次世代、次々世代の人々の生活が焦点になっています。
「開発」によって現世代の人々の生活が改善されるだけでなく、将来の世代の人々も安寧な生活を送れることを目指すのが「持続可能な開発」の視点です。温暖化ガスの排出や無計画な森林伐採などを伴う近視眼的な「開発」を進めても、現世代の人々の生活には直接的な負の影響は現れないかもしれません。
しかし、このまま「開発」進めていたら、次世代、次々世代の生活は目も当てられないようなひどい状況になっているかもしれません。そうした事態に至らないように、今現在努力することが、「持続可能な開発」に込められた第二のメッセージです。
SDGsの策定経緯
前述のように、SDGsとは「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。2000年に国連サミットで採択された2001年から2015年までのミレニアム開発目標(MDGs)の後継と位置付けられています。

MDGsが登場した2000年代初頭は、開発途上国の重債務負担が問題視されており、国際的な債務削減措置が講じられるとともに、低所得者層の貧困状況を緩和することに国際社会の注目が集中していました。
MDGsは主に人間開発分野における目標であり、貧困や初等教育、保健分野の目標が集められました。国際協力の焦点を人間開発分野に当てた効果は大きく、貧困の削減、水と衛生へのアクセス向上、母子保健の改善など、同目標の達成期限である2015年までに大きな前進がありました。
その一方で、2010年代に入ると、開発途上国の貧困問題だけでなく、気候変動、エネルギー問題、災害、国内格差など、途上国、先進国を問わず、様々な問題が地球レベルで顕在化してきました。2012年6月の国連持続可能な開発会議(リオ+20)では、環境保全と経済成長の両立を目指すことが重大課題として確認されました。そして、地球環境保全や持続可能な開発の考え方のベースが作られました。
同会議において、「持続可能な開発目標」の構成や内容を議論するためのオープン・ワーキング・グループ(OWG)の設立が決まり、翌年1月に国連の下に正式に設置されることになりました。2014年7月までに13回の会合が開催され、世界各国が5つの地域グループに分かれて政府間交渉を行いました。さらに、同時期にイギリスのキャメロン元首相等をメンバーとする首脳級のハイレベル・パネルも設立され、持続可能な開発アジェンダの構成について、国連事務総長宛てに報告書が提出されました。
そして、2015年の9月、ニューヨーク国連本部において、「国連持続可能な開発サミット」が開催され、150を超える加盟国首脳の参加のもと、その成果文書として、「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されることになりました。同アジェンダでは、人間、地球及び繁栄のための行動計画として、宣言および目標がかかげられました。この目標が「持続可能な開発目標(SDGs)」であり、17の目標と169のターゲットから構成されています。
前述のようにSDGsはMDGsの後継という位置づけです。MDGsの焦点であった開発途上国の貧困削減、人間開発という側面だけでなく、経済面・社会面・環境面の3つの側面全てに対応することが求められました。また、SDGsは開発途上国だけでなく、全ての国にとっての目標であり、地球レベルでの気候変動対策のほか、先進国における生産と消費、人権やジェンダー、雇用なども対象となっています。
SDGsの推進体制
SDGsへのコミットメントを実現するため、日本政府は2016年5月に、内閣総理大臣を本部長とするSDGs推進本部を内閣に設置しました。副本部長は内閣官房長官及び外務大臣であり、他の全閣僚が本部員となりました。SDGs推進本部は政府内の司令塔として、関係行政機関の緊密な連携を図り、SDGsの実施を総合的かつ効果的に推進する役割を担います。

そして、2016年5月のSDGs推進本部の第一回会合において、SDGs実施のための日本の指針を策定することが決定されました。同年12月の第二回会合で、「SDGs実施指針」が決定されました。このSDGs実施指針では、まずSDGs実施に向けて、「持続可能で強靭、そして誰一人取り残さない、経済、社会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者を目指す」とのビジョンが示されました。そして、このビジョンの達成に向けた取り組みの柱として次の八つの優先課題が掲げられました。それぞれがSDGsの17の目標に対応しています。
1.あらゆる人々の活躍の推進
2.健康・長寿の達成
3.成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション
4.持続可能で強靭な国土と質の高いインフラの整備
5.省・再生可能エネルギー、気候変動対策、循環型社会
6.生物多様性、森林、海洋等の環境の保全
7.平和と安全・安心社会の実現
8.SDGs実施推進の体制と手段
また、この実施指針の「付表」では、これらの八つの優先課題に取り組むために、140の施策が成果指標とともに掲げられています。SDGs実施指針とその付表は、日本のSDGs目標を各種の計画、政策、戦略の中で主流化するための行動計画と位置付けられます。
SDGsの推進に際しては、ステークホルダーとの連携をもとに進めることが、「2030アジェンダ」では求められています。日本政府も、NPO・NGO、民間企業、地方自治体、有識者等のステークホルダーとの連携を重視し、様々な取り組みを進めています。その中で代表的なものは「SDGs推進円卓会議」です。これは、関係府省庁とNPO・NGO、民間、消費者団体、労働団体等の代表から構成される会合であり、年に二回のペースで開催されています。実施指針の骨子についても、この会合で議論されました。
2017年12月の第四回SDGs推進本部会合では、「SDGsアクションプラン2018」が決定されました。その内容は、「SDGs実施指針」をベースとするものですが、新たに日本型のSDGsモデルを世界に発信することが目指されました。経団連が中心として検討している「Society 5.0」、地方自治体の「地方創生」に加え、「働き方改革」、「女性の活躍推進」といった取り組みが、こうした日本の「SDGsモデル」を構成すると提案されています。さらに、この会合で、第1回「ジャパンSDGsアワード」受賞団体も決定されました。
日本の「SDGsモデル」をどのように具体化するか、それをどう世界に発信するかが今後の課題です。それに際しては、民間企業、市民社会、地方自治体が大きな役割を担うことが求められます。
SDGsに企業が取り組む理由
SDGsは国連サミットという国際的な舞台で合意された各国における開発目標です。しかし、あくまで努力目標であり、法的な拘束力はありません。官民双方が目指すべき目標という位置づけですが、誰が推進に責任を負うのか特定されているわけではありません。財源についての合意もありません。

各国政府に対する拘束力がないのですから、まして民間企業にとっては、SDGs達成に向けて活動する義務はありません。あくまで各社の自主的な取り組みという位置づけです。それにもかかわらず、今日、数多くの日本企業がSDGsの達成に向けて強い意志を示しています。大手企業のウェブサイトを見ると、各社の事業やCSR活動とSDGsの目標との関係性が示され、いかに各社がSDGs達成に向けて真摯に取り組んでいるかがアピールされています。
企業がSDGsという国際目標の達成に強い意欲を示すのはなぜでしょうか。各社が「SDGsの精神に賛同した」というのが大きな理由でしょうが、それ以外にもいくつか理由があるように考えられます。その第一は、非財務的視点での企業価値の見直しです。投資家が企業の価値を測る材料として、これまではキャッシュフローや利益率などの定量的な財務情報が主に使われてきました。しかし、これに加え近年では環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の三つの視点から、非財務的情報を考慮する投資の在り方(ESG投資)が注目されています。
環境、社会、ガバナンスの面で脆弱な面を持つ企業は、中長期的な持続的発展性に欠けるとみなされ、中長期的な観点での投資には不向きであると判断されます。例えば、石炭や石油等の化石燃料に依存するビジネスは、世界的な地球温暖化防止の潮流の中で、中長期的には持続しない可能性が高いです。
そのため、こうした企業から投資を撤退する動きがすでに顕在化しています。SDGs目標とESG投資の観点は一致する部分が多く、企業はSDGs達成への取組みを強調することで、E,S,Gのそれぞれの観点での非財務的企業価値が高いことを示すことができます。
第二は、SDGsコミットメントの波及的拘束効果です。前述のように、SDGsは国際的な努力目標であり法的拘束力はありません。しかし、SDGs達成に関連する法令が各国で制定されれば、それに基づく法的拘束力が発生することになります。
例えば、SDGsの目標8のターゲット8.7は強制労働や児童労働の根絶を目指しています。これを受けて、英国では強制労働や人権侵害を防止する法律である「Modern Slavery Act(現代奴隷法)」(2015年)が制定されました。対象は、世界での売上高が3600万ポンド(約50億)を超えて、英国で活動する企業です。企業は自社のサプライチェーン上で、強制労働や人身取引といった人権侵害のリスクを根絶することを求められます。
もし、日本企業が英国企業のサプライチェーンの中にあるのであれば、途上国の含め自社が関連する事業所において、強制労働、児童労働等がないことを示さなければなりません。それができなければ、英国企業へ納品を続けることができなくなるおそれがあります。英国と同様の動きはフランス、米国、豪州等にも広がっており、グローバルに展開する企業の事業を拘束することになっています。
第三は、SDGsへの取り組みを通じた事業機会の拡大です。世界経済フォーラムが2017年に発表した報告書「より良きビジネス より良き世界」によれば、SDGsの達成を目指すことを通じて、2030年までに世界で年間12兆ドル以上の市場機会が創出されます。特に、「食料と農業」、「都市」、「エネルギーと材料」、「健康と福祉」の四分野において、事業機会が大きいとの指摘があります。
さらに、国連グローバルコンパクトとKPMGが2016年に取りまとめた「SDG Industry Matrix – 産業別SDG手引き」でも、SDGsがもたらす事業機会について、産業ごとに事例が示されています。企業がSDGsの達成に向けて取り組むことで、国内外で大きな事業機会が生まれる可能性があります。
第四は、SDGsの官民両者の、そして世界共通言語として有用性です。SDGsは企業が取り組む課題であると同様に、世界各地の中央政府や自治体が達成を目指す目標です。企業が環境、社会、経済面で開発への貢献が大きな事業や活動を推進する場合、SDGsの枠組を使って、その効果を行政府にアピールすることができます。行政府が事業の価値を高く評価することになれば、当該事業の推進は行政府の「お墨付き」を得ることになりえます。開発途上国での事業であれば、国際機関などの開発協力プログラムの中で位置づけられ、資金的補助を受ける可能性も生じてきます。世界共通言語としてのSDGsを戦略的に活用することで、事業の拡大が進めやすくなります。
SDGs自体は国際的な努力目標に過ぎませんが、こうした四つの要因があるため、企業としては真摯に取り組むべき課題と受け止められています。
SDGsがもたらす途上国でのビジネスチャンス
日本は世界各地の開発途上国と経済的なつながりが大きく、日本企業も貿易や投資を通じて途上国の市場や産業と深くかかわってきています。途上国の地域社会を単にビジネスの対象としてみるのではなく、現地の社会・経済的問題の解決に能動的にかかわろうとする試みが増えています。

近年の開発途上国の経済成長は目覚ましいものがありますが、地域社会には成長に取り残されているところも少なくないです。日本企業の技術、ノウハウがこうした地域の問題解決に向けて、有効に役立つ場面が多々あります。
一昔前は、現地の社会問題の解決に向けた企業の活動は、企業の業務とは関連するものの、本来業務の一環というよりも、現地社会や日本国内でのブランドイメージの向上のために展開されているケースが多かったです。しかし、企業戦略の大家であるハーバード大学のマイケル・ポーター教授がCSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)という概念を提唱して以来、従来の社会貢献型活動を本来業務の中に積極的に位置付けるという発想が注目されるようになりました。
途上国での社会貢献型活動の対象である貧困層は、購買力こそ限られているものの、大きな市場を形成しています。年間所得が3,000ドル以下の人々を貧困層と見なすと、その総数は約40億人、世界人口の72%を構成します。開発途上国の経済発展により、こうした人々の購買力が高まれば、いずれは大きな市場になってゆくことが見込めます。
このような貧困層の市場はBOP(Base of Pyramid)と名付けられています。CSVとは、このBOP層の社会・経済問題の解決に取り組み、将来の大きな市場を取り込もうとする事業と考えられます。ESG投資への関心の高まりの中で、開発途上国における企業の経済、社会、環境面の事業が、投資家からも積極的に評価されつつあることも、CSV事業の推進の追い風になっていると考えられます。
SDGsとCSV事業
開発途上国におけるCSV事業は大きなビジネスチャンスを期待できるものの、実際にはチャンスを十分に活かしきれていないケースが少なくありません。限定された地域では普及していても、国内全域をカバーするような面的な拡大が実現できていない事業が多々あります。

たとえば、B to B型のビジネスの場合、当該国での製品やサービスの仕様が、既に欧米企業に有利なように設定されており、日本企業が新規に参入しにくい状況が出来上がっている場合があります。開発途上国は欧米諸国の植民地であったケースが多く、仕様等の設定に際しては、旧宗主国である欧米諸国の企業の影響が大きかったのは必然といえます。日本企業の製品やサービスを広く普及させるためには、仕様等の見直しを政府に求めることは必要ですが、これは容易なことではありません。
さらに、B to C型のビジネスの場合、中国企業の安価な製品との競合が見られます。日本企業がCSV事業で供給する製品は、中国製の競合品と比べ、品質や耐久性の面で優れていると言われます。しかし、価格面では中国製品に勝てず、貧困層が顧客のBOP市場では、その真価が認識されにくい状況にあります。
日本企業が供給する製品の方が、競合品と比較して、社会問題の解決のために効果的であることが明らかであっても、それが広く認識されない限りは、当該製品の普及には限界があります。日本企業の製品の価値を、何らかのプログラムを通じて、広く周知してもらう必要があります
開発途上国において、日本企業の製品やサービスを広く普及させてゆくためには、B to B型であっても、B to C型であっても、行政への働きかけが有効です。しかし、民間企業が自社の製品やサービスを普及させるために、行政側に働きかけるのは容易ではありません。方法を間違えると、現地政府の公務員に対する贈収賄のような形になってしまいます。現地政府の幹部職員から、そうした働きかけがあるケースも十分にあり得ます。
行政への働きかけをスマートに進めるには、SDGsを使うのが良いと考えられます。SDGsは、開発途上国でも大きなテーマになっており、目標の達成は政治的に重要な課題です。行政機関は、自らのプログラムがどのようにSDGs達成に結び付くかを示す必要があります。
日本企業の製品やサービスが、特定のSDGsのターゲットを達成する上で効率的、効果的であることを実証できれば、あるいは論理的に説明することができれば、現地の行政機関が強い関心を示すと考えられます。そうすれば現地の行政プログラムを通じて、日本企業の製品やサービスの普及を進めることもあり得ます。
たとえば、日本企業が、自社の衛生器具がSDGsの目標6のターゲット6.2に貢献することを示せば、ターゲット6.2の達成を目指している現地政府の関心を集めることは必至です。公的な保健衛生プログラムの中にその衛生器具の活用を含めることができれば、全国で当該製品が普及することが見込まれます。
SDGsは先進国、途上国双方が、さらに政府と民間セクターの双方が共通して取り組む課題です。すなわち、SDGsはそれぞれの「共通言語」として使われます。日本企業が自らの製品やサービスの効果をアピールする上で、SDGsは恰好のツールとなります。
SDGs官民連携プログラムの活用
また、現地政府への働きかけは、日本企業が単独で行うよりも、日本政府のODA(政府開発援助)のスキームの中で進めるほうが効果的です。国際協力機構(JICA)には、開発途上国における日本企業のビジネスを促進するための、官民連携型プログラムがいくつかあります。こうしたプログラムを活用して、現地政府の行政機関をカウンタパートとして参画を促すことができれば、ODA事業の実施を通じて日本企業の製品やサービスの価値を現地側に認識してもらうことできます。

例えば、過去に日本の某医療機器メーカーが開発途上国で、ある医療技術の普及を図ろうとしたことがありました。この技術は日本では広く使われ、効果が立証されていますが、当該国では普及しておらず、医療機関に受け入れてもらうことが困難でした。そこで、当該メーカーはODAのプログラムを活用して、現地の保健省の高官や医療関係者を日本に招き、技術普及のための研修を実施しました。また現地に日本人専門家を派遣し、医療関係者をあつめたセミナーなどを実施しました。こうした活動を通じて、日本の医療技術は現地で採用されることになり、当該メーカーの医療機器の信頼性が現地で高まることになりました。
日本には、これまで長年ODAの推進を担ってきた開発コンサルタント業界が存在します。この業界には、世界各地の途上国で調査・研究や技術協力プロジェクトを進めてきた人材が豊富に蓄積されています。ODA事業は現地政府をカウンタパートとすることが多いため、業務を通じて、現地政府内の中枢的な人材と幅広く厚いネットワークを作っています。
また、ODA業務であるため、外務省、経産省といった中央省庁やJICA、JETROのような公的機関の意向を受けて実施することになります。そのため、当該国における日本政府側の方針や意向などを把握しています。官民連携プログラムの傾向についても承知しています。企業がODAの官民連携プログラムを活用して、途上国市場に参入するには、こうした開発コンサルタントの有するネットワークや経験を積極的に活用するのが、効果的であると言えます。